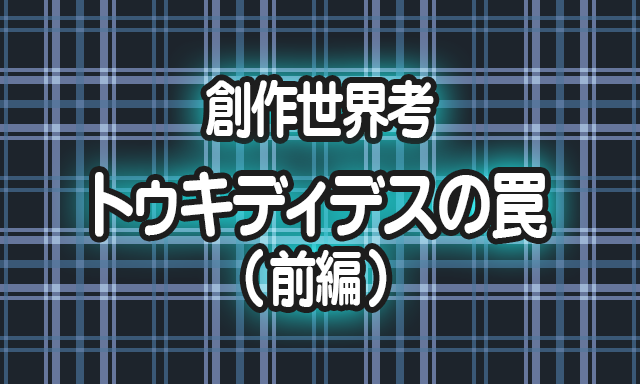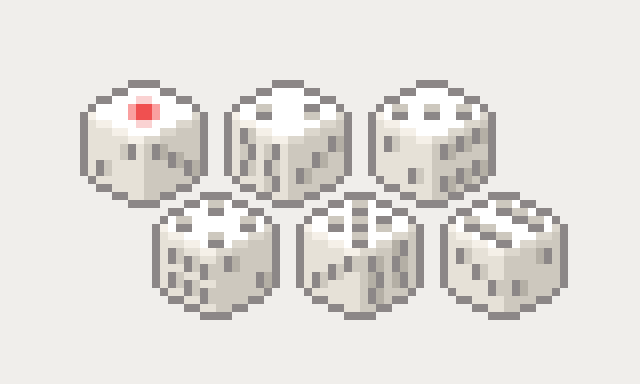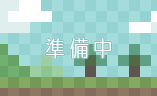紀元前5世紀に古代ギリシャで起きたペロポネソス戦争のように、新興国の存在が覇権国を脅かすことで戦争の危機が高まる――国際政治学者でハーバード大学教授のグレアム・アリソンは、この現象をペロソネソス戦争に従軍した歴史家の名に因んで『トゥキディデスの罠』と呼びました。
この『罠』は戦争のような大事に限らず、あらゆる場面に潜む普遍的なものです。前回の記事では「追われる者」が"不安"に陥る例を挙げましたが、いずれも当事者が抱える"本音"を表に出さないケースでした。本人も、自分の不安がどこから来るかわかっていないこともあるでしょう。
しかし、本音を隠さないケースもあります。
例えば、移民や外国人労働者を嫌ういわゆる「排外主義者」と呼ばれる人たち。ヨーロッパの国々で特に目立つ存在ですが、もちろん日本にもいます。彼らは一様に、そして堂々と「自国民の地位喪失(仕事を失う)の危機」を外国人排除の理由として挙げ、強く訴えます。いったい何が違うのでしょうか?
同盟者の影響
大きな違いのひとつは、"同盟者"の存在にあります。
台頭する新興国アテネに不安を抱いた覇権国スパルタも、いきなり戦争を始めたわけではありませんでした。軍事対決に慎重で、当初は"静観"しようとしたのです。
しかし、アテネは単独の国家ではなくデロス同盟の盟主であり、スパルタもペロポネソス同盟の盟主。いくら強大な同盟に属していても、それぞれの同盟諸都市は自信をもって脅威を退けられるとは思えませんから、盟主に対して"対応"を求めます。そうして、そそのかされた盟主は、同盟者への信頼のために立ち上がるしかない状況に置かれていきます。
「転校生がなんだかムカつく」ということはあっても、ひとりでできることは冷たく接することくらい。ところが「あいつムカつくよね」と言い合える仲間が見つかれば、「あいつのこと無視しようよ」という声があがり、そして仲間とのつながりを維持しようとその提案を受け入れ、やがて行動がエスカレートしていく様子は容易に想像できます。
あえてひとことで雑に言えば「集団心理」に過ぎません。ただ「集団心理」という言葉は、かなり遠目に客観視して「集団の中身を見ない」用いられ方をするので注意が必要です。たしかに現実ではなかなか集団の内側を見通せませんが、だからこそ創作では、集団の中身に存在する"ロジック"を見せることが重要になります。
また、集団を大雑把に捉えることで実体以上に「大きな存在」と見なすことは不安を高めることになります。事実に基づかない、噂にすぎない情報を真に受けやすい人や集団ほど、"敵"がより強大に見えてきて、なにかしらの行動を取らずにいられなくなります。このようなことも、『トゥキディデスの罠』に深く関わる要因とひとつとして創作に活用できることでしょう。
自信と不安のジレンマ
脅威が迫っているとき、自信がない人は不安に陥りますが、自信がないので行動できません。逆に自信がある人は不安に陥らないので、行動の必要性を感じません。脅威は存在していたとしても、はじめはこのような"静"の状態にあります。これは現実でも創作でも同じで、緊張状態を破って"静"から"動"へと変化するはそれなりの理由が必要になります。
変化のきっかけになるのは、不安当事者の"自信"と"不安"のバランスの変化です。
自信と不安の変化には、ふたつの方向性が考えられます。ひとつは"不安を解消"するもので、これは事態を平穏に向かわせることでしょう。前述の例でいえば、美少女転校生にはすでに彼氏がいたとか、優秀な新入社員が実は転職を考えているとか。
もうひとつは"行動を支える"もので、当然これは事態を争いへと向かわせます。美少女転校生が何か失敗をして責める理由ができたり、新入社員を嫌っている上司がほかにもいることがわかったり。
あるいは逆に、きっかけがなく緊張状態が続くことも考えられます。この場合、不安の解消もできず、行動も支えられないので同盟に"ほころび"が生じることが考えられます。
フィクションでは"動への移行"を見たい
『トゥキディデスの罠』を知り、緊張を招く"事態"の背景にジレンマが存在することを意識すると、フィクションにおける世界設定や登場人物の設定に必要なことが浮き彫りになります。
物語の主題が戦争であれ恋愛であれ、なにかしらの"火種"があり、行方を決定づける当事者がいるところまでは"静"であり、背景です。
そこに物語を"動"へと移行させる要因が現れ、物語は動き始めます。その役割を主人公自身が担うこともあれば、別の何かによって引き起こされることも。
創作では、現実では見えないことが多い"静"から"動"へと移行する瞬間やその理由がきちんと描かれることが重要です。"静"の状態を丁寧に描くことで、小説やマンガの読者、ゲームのプレイヤー等の観客は"動"を予想します。
そして、予想が当たって喜んだり、外れても道理に合った説明がなされることで納得できれば「おもしろい」と感じます。しかし逆に、予想が外れたうえに納得できなければ「つまらない」という気持ちになります。
難しいのは、予想があたってばかりの作品も「観る価値ない」と思われることです。それを避けるには、いかに「要所で予想をはずさせつつ、それでいて納得してもらうか」が重要になりますが、残念ながらその方法について簡単な答えはありません。世の中にはすでに多くの名作が存在し、様々な展開が"既存のもの"になっていますから、斬新なものを生み出すことは日に日に難しくなるばかりです。
それでも、この記事を読んでくれたあなたが斬新な物語を生み出すことで"創作の世界の新興国"となり、ライバルたちを『トゥキディデスの罠』に陥れることを期待せずにはいられません。"静"から"動"への移行に、期待します。